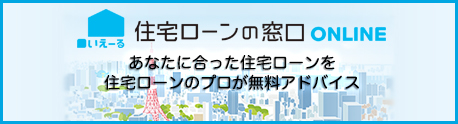こんにちは、ブロガーの千日太郎です。家を購入するときには、1割の頭金を入れた方が良いと言われています。しかし、一方で不動産のチラシにはフルローンの場合の毎月の返済額が書いてあって、頭金が無くても無理なく買えそうな感じを受けることも確かです。
ではホントのところ、頭金は要るのか要らないのかどっちなのでしょうか?今日は家を買う時の頭金のホントのところをお話ししようと思います。
家を買うときにかかる代金以外の費用
家を購入するには様々な手数料に加えて税金が必要になります。また引っ越し費用も必要ですね。
住宅ローンは原則として家の価格以上には借りることが出来ません。例外的に出来る場合もありますが、その代わりに適用金利が高くなるデメリットや、審査が厳しくなって借りられる金融機関が限定されるなどのデメリットがあります。
なので、家の代金以外の費用は現金で用意するつもりで計算しておく必要があります。家を買うときにかかる費用は、大きく分けて家の購入費用と住宅ローンの費用に分かれます。
家の購入費用
| 項目 | 計算方法 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 中古物件や建売り戸建てなど、仲介会社を通して物件を購入する場合、仲介会社に払う手数料。 「物件価格の3.24%+6万4800円」が上限。 |
印紙税 | 売買契約書に貼る印紙でその契約価格による。 1千万超 5千万以下:2万円 5千万超 1億円以下:6万円 |
| 不動産取得税 | 不動産を取得した際に一度だけ払う税金で、原則として土地建物の4%だが軽減措置でゼロ円になる場合もある。 |
| 司法書士報酬 | 所有権の保存登記を司法書士に代行してもらうための報酬。 所有権保存登記:3万円~5万円 |
| 登録免許税 | 住宅用家屋の軽減税率が適用される間は下記の税率になる。 所有権保存登記: 新築:土地0.15% 建物0.15% 中古:土地0.15% 建物0.30% |
| 土地家屋調査士報酬 | 新築の場合のみ必要。司法書士による登記と同じタイミングに司法書士事務所の土地家屋調査士が行うケースが多い。 概ね5万円~10万円。 |
| 合計(概算) | 新築の場合:家の価格の0.15%+12万円 中古の場合:家の価格の3.7%+12万円 |
住宅ローンの費用
| 項目 | 計算方法 |
|---|---|
| 融資手数料 | 銀行のホームページから情報を 入手することが出来る。 大手銀行:一律32,400円(税込)が多い。 ネット銀行:融資額の2.16%(税込)が多い。 |
保証料 | 大手銀行:銀行のホームページや担当者から情報を入手することが出来る。 ネット銀行:原則としてゼロ円。 |
| 印紙税 | 住宅ローン契約書に貼る印紙で借入金額による。 1千万超 5千万以下:2万円 5千万超 1億円以下:6万円 |
| 司法書士報酬 | 抵当権の設定登記を司法書士に代行してもらうための報酬。 抵当権設定登記:3万円~5万円 |
| 登録免許税 | 住宅用家屋の軽減税率が適用される間は下記の税率になる。 抵当権設定登記:住宅ローン借入額の0.1% |
| 合計(概算) | 借入金額の2.3%+8万円 |
その他
| 項目 | 計算方法 |
|---|---|
| 固定資産税等精算金 | 引渡し日から12月末までの金額を日割りで計算する。(4000万のマンションの場合、年間で16万円前後が目安。) | 管理費等の精算金(マンション) | 引渡し日から月末までの金額を日割りで計算する。 |
| 保険料 | 火災保険、10年一括で5万円~10万円。 |
| 引越し費用 | 5万~20万くらい、繁忙期かによっても違う。 |
頭金ゼロのフルローンで幾らの自己資金(貯金)が必要か?

まとまった自己資金が必要
家の価格が決まれば、自ずと概ね必要な費用が計算できます。2000万円から8000万円で作ってみました。
家の価格=借入金額のフルローンとする。
住宅ローンは35年元利均等返済ボーナス払い無しで借り入れる。
(単位:万円)
| 家の価格 | 新築マンション、注文住宅 | 建売り戸建て | 中古マンション、戸建て |
|---|---|---|---|
| 2,000 | 83 | 154 | 151 |
| 3,000 | 117 | 221 | 218 |
| 4,000 | 151 | 287 | 285 |
| 5,000 | 195 | 363 | 357 |
| 6,000 | 237 | 437 | 432 |
| 7,000 | 271 | 504 | 499 |
| 8,000 | 305 | 570 | 566 |
上記の数字は、前述の費用を積算したもので、ホントに必要最低限の支出しかしない場合の計算です。
例えばカーテンなどはせっかくだから新品で、新居の窓のサイズに合ったものを付けたいと思う人が多いと思いますが、その費用は上表には入っていません。カーテンだけでなく新居用に家具や家電を新しくするケースが多いです。エアコンなどは10年も経つとそろそろ寿命ですし、持って行って設置するより、新しく買った方が経済的だというケースも多いですよね。
そんなこんなで100万位はすぐ行きます。頭金ゼロのフルローンで借りる場合でも、それなりにまとまった金額の現金が自己資金として必要ということです。
一割の頭金を入れる場合に幾らの自己資金(貯金)が必要か?
さらにこれに対して1割の頭金を入れるとすると、以下のような金額になります。
家の価格の1割を頭金として9割を住宅ローンで借りる。
住宅ローンは35年元利均等返済ボーナス払い無しで借り入れる。
(単位:万円)
| 頭金1割 | 新築マンション、注文住宅 | 建売り戸建て | 中古マンション、戸建て |
|---|---|---|---|
| 2,000 | 279 | 350 | 346 |
| 3,000 | 411 | 514 | 511 |
| 4,000 | 542 | 678 | 676 |
| 5,000 | 683 | 852 | 845 |
| 6,000 | 823 | 1,024 | 1,018 |
| 7,000 | 955 | 1,188 | 1,183 |
| 8,000 | 1,087 | 1,352 | 1,348 |
同じく、必要最低限の費用だけを積算したものです。結構な金額になってきますよね!
中古の戸建ては頭金を入れた方が審査に通りやすい
住宅ローンを融資する銀行は、審査の際に融資率(融資額÷物件担保価値の割合)を確認します。
融資率が小さい(=物件の担保価値に対して融資額が少ない)ならば担保物件を売却して貸金を回収できる可能性が高いという判断をします。
特に中古の戸建てに関して、銀行は建物価格をかなり低く評価する傾向があるので、希望の融資額に届かないというケースもあるのです。頭金を1割ほど入れておくことで審査に通る可能性を上げられます。
新築住宅は市場価格が2割下がるので頭金を入れた方が安全
住宅ローンのリスクとその対策という側面から考えた場合、頭金を入れた方が安全です。特に新築住宅でその傾向が高くなります。
家計バランスシートを用いて分かりやすく解説しましょう。バランスシートは日本語では貸借対照表といい、企業の決算日時点の財政状態を一覧表示する決算書の一つです。家計の財政を一覧するのが家計バランスシートです。
左側が資産で現金預金や機械や備品、不動産などを書きます。
右側が負債で借金つまり住宅ローンです。
資産と負債の差額が純資産です。

家計バランスシート
例えば、会社であればこの純資産がマイナスになることを「債務超過」といいまして、高い確率で倒産(破産)してしまいます。
フルローンで家を買った瞬間の家計バランスシートは家の価値=住宅ローンです。
その後、家の価値は使用と経年劣化によって下がっていきます。
住宅ローンは返済によって減少していきます。
家計バランスシートでは債務超過になっても破産することはありません。毎月の返済を継続していられれば、何の問題もなく続けられるのが個人の家計です。
家計バランスシートは仮に住宅ローンの毎月の返済を継続できなくなった時にどうなるのか?という表です。
新築住宅の場合は、買った瞬間に中古になり、市場価値が2割ほど下がると言われていますよね。つまり、新築住宅をフルローンで購入した場合は最初からいきなり債務超過になってしまうケースが多いのです。
もちろん、前述したように家計バランスシートは債務超過になっても、住宅ローンの約定の返済を続けられる限りは何の問題もないのですが、もしも返済が継続できなくなった場合には家を売却しても借金だけが残ってしまうというリスクを負い続けることになります。
もしもの時のリスクを小さくする保険という見地から、頭金を1割程度入れておくことがお勧めなのです。
住宅ローン減税の恩恵をフルに受けたいなら頭金ゼロのフルローンか?
しかし、一方で住宅ローン減税というものがありますね。これは年末の住宅ローン残高の1%がその年の所得税及び翌年の住民税等から還付される減税制度で、最長10年(消費増税後は13年)受けられるものです。
住宅ローン残高の1%がキャッシュバックされるので、ローン金利が1%未満の場合は借入が多い方が儲かってしまう!という現象が起きています。
なので、頭金に入れる貯金があるのだけど、あえて住宅ローンをフルローンで借りるという人がいます。これは確かにその方がお得になります。ただし、住宅ローン減税には二つの上限がありますので、それを確認した上で借入額を決めましょう。
- 家の種類による上限(認定長期優良50万、一般住宅40万、中古20万)
- 住宅ローン減税を受ける人の所得による上限
住宅ローン減税は税額控除です。税額控除は納める税金からマイナスするということです。つまり、低所得だと払う税金も少ないですから住宅ローン減税の上限も低くなってしまうのです。
そこでざっくりした早見表を作りました。税引き前の額面年収と所得税、住民税、それに対する住宅ローン控除の目安は以下の通りです。
(単位:万円)
| 年収 | 所得税 | 住民税 | 住宅ローン減税 |
|---|---|---|---|
| 200 | 3 | 6 | 9 |
| 300 | 6 | 12 | 17 |
| 400 | 9 | 18 | 22 |
| 500 | 14 | 24 | 28 |
| 600 | 20 | 31 | 34 |
| 700 | 32 | 38 | 46 |
| 800 | 48 | 46 | 50 |
| 900 | 63 | 54 | 50 |
| 1,000 | 80 | 62 | 50 |
| 1,100 | 99 | 72 | 50 |
| 1,300 | 143 | 91 | 50 |
| 1,400 | 175 | 100 | 50 |
| 1,500 | 205 | 109 | 50 |
注:家の種類による上限は認定長期優良又は低炭素住宅の50万円としています。
なので、年収500万の人が4000万円の住宅ローンを借りても、1%の40万円の税金がかえってくるのではなく、28万円で頭打ちになるのです。こうして借り過ぎを抑制する効果もあるんですよね。
また、年収700万円を超えた辺りからは、幾ら借りても減税は頭打ちとなっています。高収入の人を優遇し過ぎないようにしているんですね。
なので、自分の年収で無理なく買える価格の家で幾らの住宅ローンを借りるのか?この表の範囲内で借入額の上限を決めるようにすれば、あまり極端な住宅ローンの借り方にはならないはずです。
やっぱり頭金はいくらか入れることになるでしょう。住宅ローン減税のためにフルローンで借りる方がおトクという場合は、年収に対して購入する家の価格に余裕があるケースになると思います。
まとめ

お得に家を買うには?
これまではずっと人口は増える一方でした。人口の増加とともに経済は拡大していきました。しかし、これからの少子高齢化社会は違います。人口が減っていく、それも戦争や自然災害などではなく自然に減っていく、というのは人類がいままで経験したことの無いことです。
そんな環境下で、どうやって自分や家族を守るのか?その明確な答えはありません。しかし、住まいを手に入れるというのは、こうした長期的な視野をもってやらなければならないことです。この「正解」というものはまだこの世にありません。
私が書いた『家を買うときに「お金で損したくない人」が読む本』では、その正解のない問いに正面から答えることを目指しました。ぜひ、お手にとって読むに値する本なのか確認してください。
全国の書店と通販で発売中です。千日太郎に出会った皆様が、家と住宅ローンで賢い選択をして素敵な人生を送られることを願っています。